|
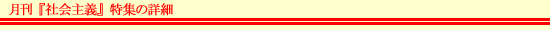
●2023年3月号
■ 最近の経済に関する疑問を解きほぐす
伊藤 修
■ 最近の経済の動きの要点
この稿は表題のとおりのテーマを扱う。最初に近年の経済動向の要点をふりかえっておこう。なお以下は2月14日現在までの状況にもとづく。
変動の出発点は2020年はじめで、世界的にコロナ感染が爆発した。このため、需要の面で飲食、旅行、運輸、商業など、人が集まる性格の消費が消失した。供給の面では、国際化している部品・中間製品などの移動が止まった。これら両面から経済活動は縮小した。
落ち込みに対して各国政府は経済対策をとり、財政資金を散布、金融政策でもほぼゼロ金利にして貨幣をばらまいた。これで貨幣の出回り額が世界的に一段増加した。
22年になるとロシアがウクライナに侵攻し、ガス、石油、穀物などの供給が細って、値上がりした。
以上の経済縮小、貨幣増加、基礎物資値上がりによって、世界的に下降とインフレが並んで発生した。最悪期は過ぎたとみられるものの、まだ回復途上にある。
そして日本では急激な円安も物価上昇の要因になった。
■ 為替レート……円安? 円高?
円/ドルの交換レートは、2014年ごろ以降、1ドル=110〜120円の範囲にあったが、22年春から急激な円安になり、10月には150円まで行った。その後やや円高方向に戻り、2月なかば現在130円前後にある。
1ドル=110円から150円まで円安になった場合を例に確認しておこう。国際価格1ドルの商品を輸入したとき払う代金は、110円から150円へ大幅に上がる(円の価値が下がる=「円安」)。輸出の方は、110円の商品が1ドルだったのが、150円の商品が1ドルになるので、ドル価格を値下げして売れ行きをふやすか、値は変えずに円での手取り額をふやすことができる。
円安で、輸入の負担は重く、輸出は有利になる。両面ある。日本では円高は悪く円安は良いことだという妄信が根強いが、今回の輸入品値上がりで、どちらが良い・悪いというものではないことが、さすがによくわかったはずだ。
さらに近年は、生産拠点や貿易のグローバル化で、日→米の輸出といった一方通行でなく、日本から部品をアジアなどへ輸出し、組み立ててまた輸入、さらに加工して輸出、というふうに複雑な双方向になっているから、円安は輸出に有利と単純にいえない。
さて22年の円安はどうしておきたか。最大原因は「内外金利差」である。世界はインフレ対策で中央銀行からの貨幣の出回りを減らすため、金利を上げている(米国4.5%、欧州3%)。日本だけがアベノミクス=黒田「異次元緩和」でゼロ金利を続けているから、資金を運用するのに日本=円は損だ。当然、高金利でもうけるため、円を売ってドルやユーロを買う。売られて円は下がる(円安)。
日本の金利の方が低い状態はしばらく変わりようがないと思うが、内外金利差が縮まる(と予想される)と、逆方向へ、つまり円高方向へ動くだろう。
■ 金融……日銀の動きは?
金利というものについて、もう少し知っておこう。
ふつうの商品と同じく、貨幣にも卸売市場と小売市場がある。金利というとわれわれは預金金利や住宅ローン金利を思い浮かべるが、これは“対顧客”の小売の値段だ。業者である金融機関どうしの貨幣の取引は国債市場でやる(卸売市場)。貨幣を手に入れたい金融機関は、国債を売って代金を得る。国債を買う者は、貨幣を手放す(売る)。
国債の価格は、買う者にとって、1枚買うのに必要な投資額である(国債価格が高いときは投資額が多く必要)。国債の利子はあらかじめ決まっているから、国債が高いと、投資額に対する利子の比率、つまり収益率は低い。この収益率が国債市場の利回りで、金利ともいう。国債の高価格すなわち低金利、低価格すなわち高金利、であることを確認しておこう。
日本の超低金利とは、国債価格が超高いことを意味する。そんな高くて収益のない国債を買う者がいるか?――いる。日銀である。それをやるのが安倍=黒田「異次元緩和」だった。日銀保有は600兆円近く、全体の半分以上。
当然、採算度外視の超高値で買ってきた国債は少し値下がりして、日銀は値下がり損を抱えている。損はいま9兆円くらいだと黒田総裁は述べた。この先、20兆円を超す損が出そうだとも言っている。
この損失はいまのところ帳簿上の「含み損」「評価損」で、売らずに満期まで持ち続けるため実際に現金での大損にはならないという。しかし実質的な損失にちがいない。日銀の経営危機がありうる。公的資金投入となろう。
いまの超低金利、つまり国債の超高値をいつまでも続けることはできないし、そもそも世界最悪の政府借金(国債)累積だから日本の国債はあぶないと見られ、信用が落ちている。世界の資金運用機関、投資家、投機家が、いつ日本国債を売ろうかと機会を見計らうのは当然である。
すでに国際投機筋の一部は日本国債を売り浴びせている。まだ高いうちに売ってしまう、あるいは品借りしてすぐ高く売り、値崩れしてから買い戻して返せば、濡れ手でかせげるからだ。日銀は値崩れさせまいと「買い向かって」防戦。ついに昨年末、日銀は買い支えきれず、投機筋に敗北した。国債の値は下がった。さきの確認のとおり金利は上がる。0.25%で抑えてきた国債金利が突破され、0.5%へ防衛線を後退させた。
日本の金利が上がって、これも確認したように円高方向に動く。これが昨年末からの円高方向への戻りである。
そのあと2月はじめ、米中央銀行FRBが金利をさらに0.25%上げたが、直後に円は下落→上昇→下落と動いた。金利を「さらに上げた」と読むか、「上げ幅が小さくなった」と読むか、投機家の見方が割れて(正解はない)揺れ動いている。
3月で黒田総裁が退任し、植田和男・東大名誉教授に代わる。よほどひどいリフレ派=アベノミクス狂信者でなく常識がある限り、金利は少しずつ上げざるをえない。米欧はそろそろ利上げ打ち止めに近いだろうから、この面からは円高方向と考えられる。ただし国債暴落を避けるため、日本の金融引き締めは「だましだまし」にするしかない。
■ 財政……“ばらまき”はどうなる?
財政はばらまきがひどく、国債はさらに累積して、前述の金融の困難が財政危機とリンクして生じている。
昨年末刊の軽部謙介『アフター・アベノミクス』(岩波新書)においてなされた取材でだいたいわかったのだが、安倍元首相周辺は当初リフレ派に乗り、超金融緩和のみがデフレ脱却をすぐに実現するとの方針をとったものの、いつまでたっても全然だめなので、財政ばらまきへ重点を移したようだ。自省しない人間というのはすさまじい。
こうなると、財政赤字でも心配ないとするMMT派理論が大問題である。国債がいくら累積しても、いまは貨幣をいくらでも発行できるから、それで返済すればいい。貨幣多すぎでインフレが危険になったら引き締めればいい、という。筆者の見解は何度か述べたが、概要以下のとおり。
一般論は無効。その国がどういう経済条件にあるかで、話はまったくちがってくる。需要不足が小幅で、成長力が強く、国債が少ない国の場合は、わずかな国債増発で需要を補充し、生産も伸び、国債もたいしたことはない。これは通常のケインズ的な景気刺激策にすぎない。
反対に、需要不足が大きく、成長力が弱く、国債累積が大きい国(日本はまさにその典型!)だと、需要と生産を拡大するには巨大な国債増発=貨幣増発が必要で、国債累積は爆発する。そして走り出したインフレは、MMTがいうようには簡単に止まらない。それは古今東西の事歴(日本では戦後インフレ)で確証済みである――。
自民党は票欲しさでばらまきを続けそうなので(あとは野となれ、だろう)、われわれが右を主張するのはきわめて大事になる。なお財源の柱は所得税と法人税、負担能力の大きい者が累進的に負担する、がわれわれの原則だ。
■ 物価と賃金……インフレ下で賃上げを復活せよ
日本の輸入物価の上昇率(対前年比)は、昨年40%ほどという高さが続き、最近も20%くらい。この押し上げを受けて、企業物価(以前の卸売物価)の上昇率(同前)も直近で10%前後に達している。
さらに消費財にも値上げは波及し、消費者物価の上昇率(同)は、昨年2月まで1%未満だったのが、直近の12月統計で4%まで上がってきている。また日銀が国民に聞く「生活意識に関するアンケート調査」(22年12月調査)で、物価上昇の「実感」は平均12%、暮らしの「ゆとりがなくなってきた」が53%に達した。
物価上昇、インフレが浸透し、定着しつつあるといえる。
これをめぐって問題になる点がいくつかある。
第1は物価マインド(意識)だ。物価には、傾向が続きがちという性質がある。この20年以上、物価はこれからも下がるまま(デフレ)だろうというマインド(国民の意識あるいは予想)が深く根付いてしまったため、値上げも賃上げも抑えられてデフレが続く、という悪循環が働いた。このようにマインドは重要である。
いまのインフレはコロナとウクライナ侵攻による一時的なもので長続きしないだろうという予想なら、下向きへ戻る可能性が強い。低賃金で消費が弱いからだ。逆にインフレは根強そうだという意識だと、値上げが続きやすい。
この点、さきの日銀のアンケートでは、1年後の物価が「かなり上がる」32.5%、「少し上がる」52.5%、合わせて85%にのぼった。5年後についても同じ順に34.9%、41.8%、76.7%もある。ただ、アンケートは答えに偏りが出るかもしれないので、「物価連動国債」という手法を用いた物価上昇率の予想(BEI……説明は省略)をみてみると、これも3%くらいに上がっている。物価上昇継続の予想がかなり強い可能性があろう。デフレからインフレへ「潮目が変わった」かもしれない。
グッドハート&プラダン『人口大逆転』という、コロナとウクライナ侵攻の前にインフレへの転換を予想して的中した研究書があり、世界的に注目されている。論旨は次のとおり。――これまで数十年の世界的な物価鎮静ないしデフレ傾向は、中国など賃金・物価が極度に安い国が急成長し、安い商品が世界にあふれ出たことによるところが大きい。しかし中国などでも少子化・人口減少が顕著で、賃金も物価も傾向が変わって上向くのではないか、と。
これが正しいとはまだ断言しにくいが、一つの重要な論点だと思う。
第2は、賃金の動きとのかねあいである。直近で米国は物価上昇7%に対して賃上げ5%。まだ物価に賃金が遅れているが、欧州でも物価を上回る賃上げを要求して闘われている。世界の正道である。
これに対して問題は日本だ。賃金は長らくほとんど上がっていない。非正規の激増も要因になっている。経団連も連合も「定昇込み賃上げ率」をよく口にするが、当たり前ながら定昇は賃上げではない。定昇がない中小零細も多い。だから経済学者は「現金給与総額」統計の増減で賃金の動きをみる。それによると世界的にみて異常であり、直近に至っても1〜2%しかふえておらず、4%ほど上がっている物価を大きく下回って、実質大幅目減りである。加えて、近年の消費税率の引き上げ分が賃金にフルに反映していないなど、これまでの「宿題」もたまっている。
定昇を含まないベアで5%が最低限であり、それにどれだけ上乗せするかが、世界の目を含め常識だといえる。もちろん単年度だけが問題ではない。今年無理なところでも複数年度をつうじて、目減り回復以上を取ることだ。
第3に、価格転嫁。値上げは価格転嫁できるところでおきていて、下請け中小企業には親会社に値上げを拒否されているところが多いようだ。優越的な立場を利用して抑圧する悪質な例は不公正取引にあたる。是正指導の行政はあるが、どしどし企業の実名を公表するなどの制裁を実施している諸外国に比べ、行政が弱いと専門家は指摘する。日本の急所の1つであり、特に強化すべきである。
■ 生産性や経済力の低下を問題にすべきなのか?
日本の経済力(たとえばGDPや所得)が落ちて衰退している、先進国中で生産性が低い、などが最近問題にされている(筆者は国際比較データをみていて数年前に気づき、指摘してきた)。しかし労働者が生産性や経済力の低さを問題にするべきなのか、という疑問をもつ人もいるだろう。ここは解きほぐしておいた方がいいと思う。
まず生産性(productivityプロダクティビティ)。常識的には「労働者の能率」くらいに思われているだろうが、少し考えてみると、あいまいでよくわからない。
じつは経済学での扱いはむずかしい。定義は「投入1単位あたりの生産」である。たとえば農業の「土地生産性」というのもあり、農地の面積あたりの収穫(=反収)で、計算はもちろん「収穫/面積」。しかしこれは単純に土地の質の良し悪しを表わすと受け取っていいだろうか。機械や農民の働きは反映していないか?
いちばん問題にされるのは労働生産性だろう。計算は「生産/投入労働量」。投入労働量には何種類かあり、それらによって生産性の数字もいろいろある。いちばん広くとれば、生産は国の合計であるGDP、投入労働量は人口で、これを使えばようするに「1人あたりGDP」になる。日本の伸びは低い。厳密を期して現役労働者数を分母に使うと、生産性の伸びは先進国平均のようだ。そうであれば、全体の生産性の伸びの低さは高齢化によることになる。また人数でなく、人数×労働時間=総労働時間で割ることもあり、この方が「能率」には近いだろう。数字がいろいろで、「低い方のようだ」くらいしか言えない。
より重要なのは、生産性に影響する要素には何があるかだ。生産の伸びはようするにGDP成長率だが、それを次のように分解する分析(成長会計という)がある。
経済成長=生産設備(固定資本)の増加+投入労働量の増加+生産性の上昇、と考えて、各要素を算定する。生産性上昇は直接表われないし計測できないものだから、成長率から投入の増加分を差し引くという計算で、間接的に、残りとして生産性を求めるしかないのである。
その上で、生産性に影響するものには、メインと想定する“技術の進歩”のほかに、設備の質(新しさ)や労働力の質(教育や訓練の成果)の向上、生産性の低い産業から高い産業への比重移動、あるいは労働強化など、さまざまありうる。
かつて高度成長期に「生産性向上(マル生)反対」運動が取り組まれたのは、資本側が主に“生産性の邪魔になる労働運動の弾圧”を狙ったことに反対したのである。
こうみてくると、結論は次のようであろう。
労働者が反対しなければならないのは、もちろん、労働者へのしわよせ(条件の悪化)に対してである。つまり、失業がふえること、労働密度(強度)が高まること(および精神的にきつい労働になること)、労働時間が長くなること、賃金が下げられること、労働者の団結が弱められて職場環境が悪くなること、である。“生産性そのもの”は、上昇にも低下にも、賛成や反対をするような対象ではない。
そして、いま日本で特に問題なのは、資本側が「安いコスト」「コスト引き下げ」にだけ狂奔して依存症に陥り、「不合理、不条理、時代遅れなやり方」(教育研究の軽視もそうだ)による能率の悪さが蔓延していること、そのせいで貧困化や社会問題が深刻になっていること、である。これらは正す。結果として、生産性は上がるだろう。
経済力についても、以上と同じように、不合理なところを正す、GDP増加は目的ではなく結果、労働者のしわよせはお断り、と考えるべきだろう。
|