|
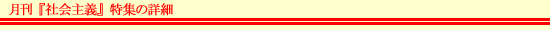
●2023年1月号
■ 低成長と「新しい資本主義」の限界
立松 潔
■ はじめに
日本経済の低成長・低生産性・低賃金が問題になっている。その対策として岸田内閣は「新しい資本主義」路線を打ち出しているが、その中心眼目は「成長と分配の好循環の実現」である。そしてそのためにはまず日本経済の成長力を高め、それによって賃金の引き上げを実現するとしている。
コロナ対策についても、ワクチン接種の拡大を背景に経済の好循環実現に向けて制限の緩和を推し進めている。観光需要の喚起策として全国旅行支援が推進され、水際対策緩和によって外国人旅行客も増加を始めた。コロナ禍で中止されていたイベントが復活し、買物客や旅行客の増加により景気も回復に向かっているように見える。しかし感染者数は増加を続けており、自主的な行動抑制による個人消費への影響はまだしばらくは続かざるを得ないであろう。
コロナ禍前の日本は1990年にバブルが崩壊してから30年以上もの長期にわたってデフレ不況が続き、その過程で企業の体質にも大きな変化が生じた。そしてその体質変化が日本の低成長・低生産性の要因になると同時に、賃金の低迷と格差の拡大をもたらしているのである。コロナ禍が終息しないウイズコロナ状態のままで、日本経済や国民生活、雇用がどう推移するのかは依然として不透明である。本稿では中・長期の視点から、日本経済の動向とその抱えている問題点について検討してみたい。
■1. 個人消費の低迷とその背景
2012年12月に成立した安倍政権のもとで、景気は2018年10月まで71カ月にわたって回復・拡大を続けた。しかし、日本の実質GDP(国内総生産)の伸びは、2012年の517.9兆円から18年の554.8兆円へと6年間で7.1%(36.9兆円)の増加にとどまっている。これは年平均1.15%の伸びに過ぎないから、低成長の6年間と言った方が良いであろう。
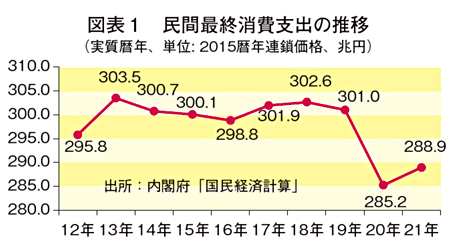
(図1・クリックで拡大します)
低成長の最大の要因はGDPの6割近くを占める個人消費の低迷である。図表1からわかるように、比較的高い伸びを示したのは、2013年の対前年比2.6%(7.7兆円)拡大の時ぐらいであり、あとは一九年まで停滞的に推移している。
2013年の消費拡大は株価上昇による資産効果によって(富裕層中心ではあるが)消費が拡大したことと、14年4月の(5%から8%への)消費税率引き上げを前にした駆け込み需要によるものであった。しかし、増税後はその反動で消費減となり、またこの時の富裕層による高級品など購入増も一時的なもので終わってしまう。その結果、個人消費は14年から16年まで3年連続で減少し、その後やや回復するものの、18年時点でも13年の水準を下回っているのである。そして19年には10月の消費増税の影響で再び減少し、20年にはコロナ禍による大幅な落ち込みとなった。
個人消費低迷の大きな要因は実質賃金の低下である。図表2からわかるように、2012年から18年までの6年間で実質賃金は3.6%も低下している。特に14年は消費税率引き上げよる物価上昇の影響もあって、対前年比で2.7%もの大幅な低下となった。この6年間で実質賃金が前年比で上昇したのは16年と18年だけで、それもわずかな上昇にとどまっていた。
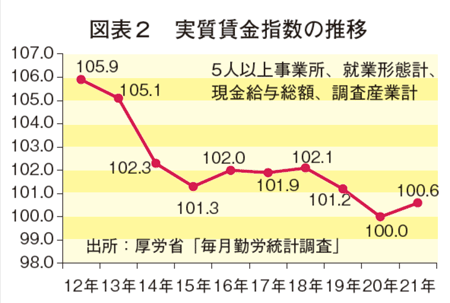
(図2・クリックで拡大します)
なお2022年4月以降、資源価格の上昇に急激な円安が加わり、消費者物価が急上昇している。この物価上昇により、21年には回復に向かっていた実質賃金は再び下落を始めたのである。22年10月時点において、対前年比で消費者物価指数は3.7%上昇、実質賃金指数は2.6%の低下となっている。
■2. 非正規雇用の増加と人材育成投資の削減
以上のように、2012年から18年までの景気拡大期は低成長だったとは言え、実質GDPは6年間で7.1%拡大していた。しかしそれにもかかわらず、同じ期間に実質賃金は3.6%も低下したのである。岸田政権の新しい資本主義実現会議は、21年11月の「緊急提言」において、「成長と分配の好循環の起爆剤として、まずは成長の実現が重要」であるとしているが、むしろ問題は経済が成長しても賃金への分配が行われていないことなのである。その原因を明らかにしないで、成長を優先しても実質賃金の上昇は実現できないであろう。
実質賃金が低下に向かったのは1997年の金融危機以降である。図表3からわかるように、97年から2012年までの15年間に、リストラや採用の抑制により正規雇用の労働者は3854万人から3311万人へと543万人(14%)も減少している。これに対し、非正規雇用の労働者は1261万人から2043万人へと732万人(62%)もの増加である。正規雇用を大幅に減らし非正規雇用を増やすことで、賃金コストの削減が進められたのである。
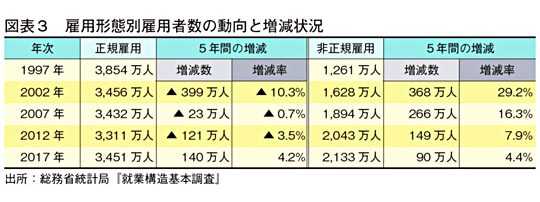
(図3・クリックで拡大します)
企業にとって非正規雇用は低賃金で解雇が容易というメリットに加え、人材育成のための研修費などの削減も意味していた。日本の人材育成投資のピークは1991年であったが、その後の金融危機とデフレ不況によって大幅に低下し、2015年にはピーク時のわずか16%になったという(宮川努『生産性とは何か』(ちくま新書、2018年、p.127)。
非正規社員が業務内容改善に向けた意見を述べたり提案をしても、会社からは十分な対応をしてもらえないことが多いと言われている。また、低賃金の定型的業務にだけ従事させられる非正規社員にとって、業務の改善や職業能力の向上への意欲が刺激されることも少ないのであろう。
しかし、生産や顧客サービスの前線で働く労働者の経験が、業務の改善に反映されないのは生産性の向上にとってマイナスである。このように、非正規雇用の増加にともなう雇用の劣化は、日本企業の生産性の停滞をもたらす要因にもなっているのである。
厚生労働省『労働経済白書』の2018年版によれば、日本の実質労働生産性はG7の中で最も低く、2012〜16年の平均値で1位のフランスの67%、6位のイギリスの89%であるという(同p.75)。そしてこのような日本の労働生産性の低さの要因として、労働者の能力開発の立ち遅れが指摘されている。たとえばGDPに占める企業の能力開発費の割合は2010〜14年平均値で日本は0.10%に過ぎず、アメリカ(2.08%)、フランス(1.78%)、ドイツ(1.20%)、イタリア(1.09%)、イギリス(1.06%)など、欧米先進国と比べて突出して低い水準となっている(同p.89)。労働生産性を高めるためには技術革新などへの投資とともに、人材育成=能力開発のための投資が必要であるが、その能力開発投資についても日本は国際的に大きく立ち遅れているのである。
また、企業で計画的に実施される職業訓練(OJT)の実施率(2012時点)において日本は男性が50.7%、女性が45.5%と、OECD平均(男性55.1%、女性57.0%)を下回り、23カ国中で男性が18位、女性が19位という低い順位になっている。労働者の能力不足に直面している企業の割合も14年時点で日本は81%に達し、OECD22カ国中最悪の水準であるという(同p.87〜p.88)。このように、日本は労働者の能力不足に直面している企業が多いにもかかわらず、企業内の職業訓練の実施率は低調なのである。正規雇用の削減と非正規雇用の増加によって、労働者の能力開発や生産性における日本の地位低下がもたらされたのである。
人材育成については、社会に出てからの教育訓練だけでなく、学校教育の過程も含めて考える必要があるが、これについても日本の状況はかなり深刻である。教育費支出のGDP比率と1人当たりGDP成長率とは密接な関係にあることが知られているが、日本政府の教育費支出のGDP比は先進国の中で最下位レベルである。経済協力開発機構(OECD)発行の「図表で見る教育」によれば、2019年時点で小学校から大学までの教育機関への公的支出がGDPに占める割合は、日本は2.8%であり、OECD平均(4.1%)を下回り、加盟37カ国中で36位だったという。
また、大学レベルの教育費の出どころについて、日本は公的負担が33%と低く、家計負担が52%にも達している。家計負担のOECD加盟国平均は22%であり、日本はその倍以上で比較可能な35カ国中で4番目に高くなっている。このような教育費負担の重さから大学進学をあきらめる若者も多く、ユネスコによれば、2018年時点の日本の大学進学率(含む短大)は、OECD平均(73.7%)を下回る63.6%であった。これも人材育成における日本の立ち遅れを示している。
■3. 企業による国内設備投資の停滞
以上のような日本企業の人材力の低下に加え、近年の日本企業が海外での投資に比べ国内での投資に消極的なことも、日本経済の低成長・低生産性の要因である。図表4で2000年以降の日本企業の投資活動を見ると、ピーク時の2018年において海外設備投資は2000年の2.7倍になっているのに対し、国内設備投資は25%増にとどまっているのである。
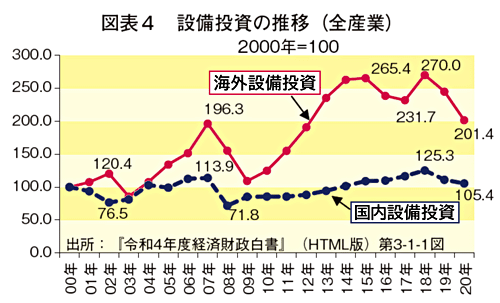
(図4・クリックで拡大します)
なお、経済産業省『第51回海外事業活動基本調査』によれば、2020年度の海外現地法人の売上高は240.9兆円である。そしてそのうち製造業が46.8%、非製造業が53.2%を占め、地域別では北米が32.2%、アジアが45.9%、欧州が14.6%を占めている。
日本銀行が異次元金融緩和で長期にわたって低金利政策を続けているにもかかわらず、借入金を設備投資に向けようとする企業も増えていない。借入金以上の現預金を保有する実質無借金企業の割合は製造業において2002年の31%から21年の58%へ、非製造業の場合は39%から61%へと増え続けているのである。(『経済財政白書』2022年度版、p.193〜p.195頁)。
製造業の場合、1990年代中頃までは円相場が輸出に大きな影響を及ぼしており、円安期には国内での増産によって輸出が拡大し、それが日本の景気を押し上げていたという。しかし、2010年代以降はそのような関係が失われ、円安期にも増産は行われなくなっている。輸出企業は円安により為替差益を得ても、かつてのようにそれを設備投資に向けることをせずに、将来の円高等に備えて内部留保として確保することを選択しているのである(古金義洋「なぜ円安でも輸出が増えないのか?」(JA共済総合研究所『共済総研レポート』181号、2022年6月参照)。
以上のように日本企業が国内での設備投資に消極的では、生産性の向上による経済成長もあまり期待できない。岸田内閣が掲げる「成長と分配の好循環」も実現は困難と言わざるを得ないであろう。
ただし、最近の急速な円安の進行によって、一部で製造業の国内回帰が注目されているのも事実である。資生堂はこの3年で国内工場を3カ所から6カ所に倍増させている。約120カ国・地域で製品を売るが、主力のスキンケア製品はこれでほぼ全てが国内生産になるという。また、アパレル大手のワールドも生産を国内工場に切り替え始めており、将来的には百貨店向けの高価格帯商品の大半を国内生産にする計画である。さらにJVCケンウッドも国内向けカーナビの製造拠点をインドネシアから長野県に移し始めているという(『朝日新聞DIGITAL』2022年8月25日)。
しかし製造業の国内回帰には障害も少なくない。円安がいつまで続くか不透明であること、少子化が進む国内の人手不足が今後深刻化する可能性も懸念材料である。いずれにしても経済成長が進むアジア地域などで、豊富な労働力を活用して地産地消の生産を行っている日本企業が、海外の生産拠点を縮小・撤退して日本国内に回帰することはあまり期待できないであろう。
このようにすでに海外で日本企業が生産しているものを国内に戻すのではなく、国内での設備投資は、新製品や新サービスの開発による生産拡大を軸とすべきであろう。また、デジタル化への投資や再生可能エネルギーなど新しい成長分野への取り組みが極めて重要であることは言うまでもない。
■ おわりに
「法人企業統計」によれば、第二次安倍政権下の景気拡大期に日本企業の経常利益は2013年から18年まで6年連続で最高益を更新していた。配当金も2012年の14.0兆円から18年には26.2兆円へと、87.8%も増えている。しかし同じ時期に1人当たりの従業員の賃金(給与+賞与)は361.8万円から366.6万円へと1.3%しか増えていないのである。
バブル崩壊後のデフレ不況下において、日本企業は積極的な設備投資によって生産性を引き上げるより、賃金コスト削減によって利益率を高めることに力を注ぐことになった。高賃金の中高年労働者をリストラし、低賃金で解雇しやすい非正規雇用を増やしていったのである。その結果個人消費は増えず、高い利益率が続いたにもかかわらず経済成長率は低水準で推移していった。日本企業にとって労働者が低賃金で我慢してくれる限りは、リスクを伴う新規の設備投資を積極化させる必要はないということなのであろう。
このような状況を転換するには、非正規雇用の処遇改善や、大幅な賃上げを要求し実現していくことが必要である。そうすれば企業は賃金コストの削減で利益を確保しようとするこれまでの安易な路線を転換し、新たな設備投資で付加価値生産性を高めざるをえなくなるからである。また、企業は労働者が賃金上昇に見合った高度な職務に従事できるよう、職業能力向上のための投資や研修機会を増やすことになるであろう。
ただし、新規の設備投資や企業による生産性向上が、労働条件の悪化や雇用の悪化につながらないよう監視することが不可欠である。物価高で国民生活が悪化している現在こそ、労働運動の力で日本の雇用の劣化を改める好機と考えるべきであろう。
|