|
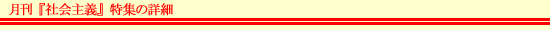
●2022年1月号
■ 「新しい資本主義」路線とその限界
立松 潔
■ はじめに
岸田首相は政権のスローガンとして「新しい資本主義の実現」を掲げ、政権発足後さっそく内閣に「新しい資本主義実現本部」を設置している。そして2021年10月26日には「新しい資本主義実現会議」(第1回)を開催し、早くも11月8日の第2回会議において『緊急提言〜未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて〜』(以下、「緊急提言」)を発表した。本稿ではこの「緊急提言」をもとに、岸田政権の「新しい資本主義」政策が登場した背景やそのねらい、問題点などを検討してみたい。
■1. 岸田政権の「新しい資本主義」路線
新しい資本主義実現会議の「緊急提言」では、最初に「新しい資本主義の実現に向けた考え方」を明らかにしている。その考え方とは、「現在、世界各国において、持続可能性や『人』を重視し、新たな投資や成長につなげる、新しい資本主義の構築を目指す動きが進んで」いること、そしてその背景は、「1980年代以降、短期の株主価値重視の傾向が強まり、中間層の伸び悩みや格差の拡大、下請企業へのしわ寄せ、自然環境等への悪影響が生じて」いるからであるという。つまり「新しい資本主義」とは新自由主義的な資本主義に対置される概念であり、岸田政権はまさにこの「新しい資本主義」を先導していくことを目指すというのである。
「緊急提言」によれば、新しい資本主義のコンセプトは「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」である。このうち「成長と分配」をめぐる問題は、衆議院選挙で与野党の論戦のテーマにもなった政策課題であるが、「緊急提言」では「成長と分配の好循環の起爆剤として、まずは成長の実現が重要である」としている。そしてその上で(成長の成果を)「従業員に賃金の形で分配することで、消費が拡大し、消費拡大によって需要が拡大すれば、企業収益が更に向上し、持続的な成長につながる」と指摘している。
しかしここでまず問題になるのは、政権が意図するような経済成長の実現が可能なのかということである。戦後の日本経済の経済成長率(実質)の動向を振り返ると、1956年度から73年度までの高度成長期には年平均成長率が9.1%、1974〜90年度の安定成長期の年平均成長率が4.2%だったのに対し、1991年度から2019年度までの28年間の年平均成長率は0.9%という低成長であった(橘木俊詔『日本の構造――50の統計データで読む国のかたち』2021年、講談社現代新書、p.29)。この低成長期のうち、安倍政権時代の実質GDPの伸びはどうかというと、2012年度の517.9兆円から2019年度の551.5兆円へと7年間で6.5%しか増大しておらず、やはり年平均0.9%の低成長に過ぎなかったのである。
■2. 生産性向上の立ち遅れ
GDPを就業者数で割ったのが就業者1人当たりの労働生産性であり、その水準を引き上げることが経済成長率の上昇のために重要である。しかし、菅内閣の成長戦略会議の「成長戦略実行計画」(2021年6月)は、その最初のページで2010年から2019年までの日本の労働生産性の伸び率は年0.3%でしかなく、これはG7諸国の中ではイタリアに次いで低いと指摘している。
生産性上昇によって経済成長を達成するには民間のイノベーション(技術革新)力の抜本的強化が必要である。しかし、1990年代半ばの金融危機(連続金融破綻)以降に深刻化したデフレ不況や2008年のリーマンショック後の世界同時不況により、日本の金融機関や企業は過剰債務や過剰設備の解消と雇用のリストラに注力し、新規投資に向かう余裕を失っていた。その後アベノミクスのもとで企業経営は上向きに転じ、日本企業の経常利益は最高益を続けることになったものの、それは生産性向上によるものではなく、円安や株価上昇の恩恵や賃金コストの削減によるものであった。
日本企業のリスクへの挑戦の気運は後退し、豊富な手元流動性(内部留保)を抱えながらも国内での新規の設備投資には慎重な状況が続いている。少子高齢化が進み、人手不足と個人消費低迷が続く状況では、国内での積極的な設備投資はリスクが高いとの判断が支配的になっているのである。円安で高収益を上げている輸出関連製造業も、依然として海外での現地生産を重視しており、国内での設備投資による輸出拡大には消極的である。
以上のような日本の生産性停滞については、新しい資本主義実現会議の「緊急提言」においても指摘されている。たとえば、付加価値の高い新製品や新サービスの投入の立ち遅れについてである。
「OECDによると、新製品や新サービスを投入した企業の割合は、日本の場合は製造業9.9%、サービス業4.9%にとどまり、ドイツ(製造業18.8%、サービス業9.0%)や米国(製造業12.7%、サービス業7.6%)よりも低い水準となっている。」
「製造コストの何倍の価格で販売できているかを示すマークアップ率を見ると、日本は1.3倍にとどまり、1.8倍の米国や1.7倍の英国より低い水準となっている。このように、日本企業は新製品や新サービスを生み出せず、十分な売値が確保できていない」(p.6)
と。
新製品や新サービスによって競争上の優位が確立されていれば、当然利益も大きく高い賃金の支払いも可能になるであろう。しかし日本では新製品や新サービスに向けた投資が不活発であるため生産性が上がらず、もっぱらリストラや非正規雇用の活用などによる人件費の引き下げで利益を確保するブラックな状況が続いているのである。
コロナ禍では、日本のIT(情報技術)分野での立ち遅れも大きな問題となった。2020年版『経済財政白書』も、IT投資について
「我が国はハードウェア、ソフトウェア共に他の主要先進国と比べて低位にとどまっている」(p.203)
と指摘している。
新技術・新製品・新サービスへの投資だけでなく、人的資本への投資の立ち後れも深刻である。「緊急提言」ではデフレ不況期以降の、日本企業の人材育成投資の状況について次のように指摘している。
「日本企業の人的投資(OJTを除くOFF――JTの研修費用)は、2010〜2014年に対GDP比で0.1%にとどまり、米国(2.08%)やフランス(1.78%)など先進国に比べて低い水準にあり、また、近年低下傾向にある」(p.13)
と。
また宮川努『生産性とは何か』(ちくま新書、2018年)も次のように述べている。
「日本におけるこの人材育成投資のピークは、バブルが崩壊した直後の1991年であった。その後徐々に低下し、1997年、98年の金融危機を経ると一層減少が大きくなった。この結果2015年の人材育成投資額は、ピーク時のわずか16%になっている」(p.127)
と。現在の日本企業が新製品や情報関連技術(IT)など新技術の導入に後れを取っているのは、このような人材育成面での立ち遅れも大きな要因である。
■3. 成長重視路線の限界
以上のように、日本企業による生産性向上のための投資は低水準に推移しており、他の先進国と比べても大きく立ち後れていた。もちろんこれに対して政府が何ら対策を取らなかったわけではない。安倍政権の時代も政府が策定する毎年の成長戦略には生産性向上のための技術革新と政府の支援策が盛り込まれている。2013年6月に発表された成長戦略(「日本再興戦略」)でも日本産業の再興に向けて、産業の新陳代謝の促進、人材力強化、科学技術イノベーションの推進、世界最高水準のIT社会の実現、立地競争力強化、中小企業・小規模事業者の革新などの方策が盛り込まれ、その多くは翌年以降の成長戦略でも引き継がれている。しかし、すでにみたように、安倍政権の下でも日本企業の国内投資は伸び悩み、日本経済の生産性上昇は極めて不十分な結果に終わっていたのである。
そして、今回の岸田内閣による「緊急提言」の成長戦略の内容も、基本的に安倍・菅政権のものを引き継いでおり、民間の生産性向上に向けた投資や新製品・新サービス創出などへの支援が中心である。しかしながらグローバル化した日本企業が、個人消費の縮小や少子高齢化による労働力不足に直面する日本国内において、どれだけ積極的に生産性向上のための投資に向かうかは不透明である。
とはいえ、低成長であることを理由に賃金切り下げを容認するのは大きな誤りである。デフレ不況期には日本の生産性の伸びが停滞的であったとはいえ、それでも少しずつは上昇していたからである。就業者一人当たりの実質GDPは2000年の748.7万円から2019年の826.6万円へと10.4%増加している。しかし、この間に実質賃金指数は逆に11.2%も低下したのである。生産性が上昇しているにもかかわらず、それを労働者に還元しようとはせず、企業は逆に賃金切り下げを強力に進めていたのである。このような企業体質のままでは、成長率を高めたとしてもその成果が労働者に還元されることはとても期待できないであろう。
賃上げに消極的な日本企業の状況については政府も認識しており、そのため安倍政権でも最低賃金の引き上げや春闘での経済界への賃上げ要請(「官製春闘」)を行っている。しかし、それにもかかわらず実質賃金指数は2012年の104.5から19年には99.8へと低下したのである(厚生労働省『毎月勤労統計調査』)。
以上から明らかなように、日本企業は賃上げが可能であるにもかかわらず成長率に見合った分配を行わず、逆に賃金を削る方向に全力を傾けていた。「緊急提言」でも指摘するように、「我が国の労働分配率は、他の先進国と比較しても低い水準」(p.1)にあり、それが個人消費を抑え経済の停滞をもたらしていたのである。
このように日本の労働分配率が他の先進国と比べ低いことを踏まえ、「緊急提言」でも民間部門における分配強化に向けた施策を提示している。その中には男女間の賃金格差解消、賃上げを行う企業に対する税制支援強化、非正規雇用労働者への分配強化に向けた施策(新しいフリーランス保護法制の立法、正規・非正規間の同一労働同一賃金の徹底、最低賃金引上げ)など、早期の実現が期待されるものも含まれている。
また岸田首相も2022年春闘に向けて、業績がコロナ禍前の水準を回復した企業に対し、3%を超える賃上げを期待すると表明し、22年度の税制改正で賃上げ企業に対する優遇税制(法人税減税)を拡充する方針を打ち出している。しかし、これによってこれまで人件費削減に注力していた企業がどれだけ賃金引き上げに応じるかは明らかでない。
労働組合の組織率が低下し、労働側の力が低下していることが賃上げが進まない要因であるが、さらに低成長下の企業間競争の激化が賃下げ圧力となっている。労働力不足にもかかわらず、中小零細企業では生き残りのために賃金引き上げに応じることが困難な企業も少なくないのである。そういう生産性の低い企業が淘汰されることで、結果的に生産性が上昇するとの「楽観論」もあるが、日本経済の現実は必ずしもそのようには動いていない。むしろ賃下げでコストを削減したブラック企業が生き残り、逆に温情的良心的な企業がコスト高で営業困難に陥るということになりかねないのが日本の現状である。労働組合が不在で劣悪な労働条件への規制が及ばないことが、そのような状況をもたらしているのである。
■4. 求められる所得の「再分配」
新しい資本主義実現会議の「緊急提言」は、所得の分配を民間部門に期待するだけでなく、公的部門での分配機能の強化をも打ち出している。すなわち、
「新型コロナウイルス感染症や少子高齢化への対応の最前線におられる、看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていくため、全世代型社会保障構築会議の下に公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格の在り方の抜本的見直しを検討する。これに先立ち、経済対策等において、必要な措置を行い前倒しで引き上げを実施する」(p.16)
と。そして11月19日に打ち出された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」では、看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く労働者の収入の引上げを2022年2月に前倒しで実施する措置が盛り込まれた。
確かに看護、介護、保育、幼児教育などの分野では労働条件が厳しいことによる人員不足が問題になっており、そういう意味でも賃金引き上げは重要である。しかし問題はそのための財源の確保である。一時的には赤字国債によって対応しても、いずれは恒常的な財源を確保することが不可欠である。しかし、これによって低所得世帯の負担が増大するようでは問題である。
これまでのように企業利益優先の賃金抑制策が続き、高齢化に伴う年金、介護、医療などへの国民負担が増加するようでは、今後ますます格差が拡大し、個人消費も低迷することにならざるを得ない。このような状況を克服するには、経済成長の果実の分配(トリクルダウン)に期待するだけでなく、富裕層の社会的負担を増やし、それを社会保障の充実に用いる所得の再分配こそが不可欠である。
財務省の資料によれば、日本の個人所得課税の対国民所得比は2018年度で8.3%に過ぎないのに対し、
- アメリカ 12.8%、
- イギリス 12.5%、
- ドイツ 14.0%、
- フランス 18.9%、
- スウェーデン 20.1%、
- ノルウェー 13.1%、
- フィンランド 17.7%
など、他の先進国は日本よりかなり高くなっている。特にスウェーデンなど福祉の充実した国では累進的に高所得者に課税する累進所得税が社会保障財源の確保に大きな役割を果たしているのである。
格差拡大と貧困世帯の増加が問題になっている現代の日本では、まずは富裕層への負担増を中心に個人所得税収を欧米並みの水準に引き上げることによって社会保障を充実させることが必要である。こうして国民の将来の生活への不安が軽減されれば、個人消費の回復にもプラスに作用することになろう。
岸田首相は自民党総裁選の段階では格差問題への取り組みを重視する姿勢を示しており、そのための政策として金融所得課税適正化を掲げていた。現在の日本の所得税率は5%から45%までの7段階の累進課税となっているが、株式売却益など金融所得は例外的に一律20%の低税率による分離課税である。一般的に高所得者ほど所得に占める株式売却益など金融所得の割合が高くなっているため、所得が1億円を超えると所得税負担率が下がることが国税庁の資料からも確認されている。
しかも安倍政権の株価重視政策によって日経平均株価は安倍政権発足直前の2012年11月の9446円から21年12月には2万8438円(いずれも月初日の終値)へと3倍にも高騰している。株式投資で多額の金融所得を獲得した富裕層が少なくないことが窺えよう。
このような富裕層優遇の金融所得課税を見直すことは、格差是正という観点からも実に適切な政策である。しかしそれにもかかわらず、政権発足後の岸田首相は早々と金融所得課税適正化への取り組みを撤回してしまう。金融所得課税の見直しが株価の下落をもたらし、政権への支持率が下がることを恐れたのであろうが、これによって格差問題への取り組みが大きく後退したのは明らかである。しかも岸田政権は累進税率の引き上げによる社会保障財源の確保にも消極的である。これでは国民の将来への不安も軽減できず、個人消費の回復も期待できない。
以上のように、岸田内閣の「新しい資本主義」路線は所得の再分配を否定し、格差問題には経済成長によるトリクルダウンで対処しようとする従来までの政策と何ら変わらないものである。しかもこのような路線はこれまでもほとんど効果を上げていない。トリクルダウン路線に決別し、所得の再分配による格差是正を推進する政策こそが求められているのである。
|