|
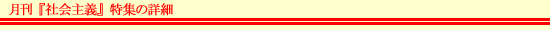
●2018年8月号
■ マルクス生誕200年と先祖返りする資本主義
立松 潔
■ はじめに
マルクスが生まれたのは200年前の1818年であるが、当時はイギリスで資本主義経済がまさに確立しようという時であった。イギリスの産業革命は1760年代に始まり、機械制大工業が繊維(織物・紡績)工業を中心に拡大し、1825年に最初の過剰生産恐慌が起きている。そしてその後も1836年、47年、57年、66年と、ほぼ10年周期で恐慌が勃発した。資本主義経済を特徴付ける周期的景気循環である。
マルクスが1836年にベルリン大学に入学した頃、イギリスではすでに資本主義が確立していたが、ドイツはイギリスと比べ資本主義化はかなり遅れていた。しかし、1840年代になるとドイツの産業経済も発展をとげ、封建制を打ち破ろうとする勢力も力を増しつつあった。そして大学卒業後左翼的な評論・執筆活動を行っていたマルクスは、プロイセン政府によって1845年に国外追放処分を受け、パリに亡命を余儀なくされる。しかし1年と少しでそのパリからも追放され、マルクスはブリュッセルに移っている。
当時のヨーロッパでは革命の機運が高まりつつあり、マルクスは1847年に共産主義者同盟から依頼されて共産党宣言の執筆を行い、48年1月に完成させている。マルクスとエンゲルスの新しい世界観がフランス二月革命、ドイツ三月革命が勃発する直前に世界に向かって明らかにされたのである。マルクスが30歳になる直前のことであった。しかし、フランス、ドイツにおける革命の波は1849年には退潮に向かい、同年8月にマルクスもロンドンに亡命を余儀なくされる。マルクスはその家族とともに、これ以降貧困の中で生涯ロンドンでの亡命生活を続けることになるのである。
ヨーロッパの革命的人民闘争は1850年以降沈静化を余儀なくされ、マルクスは経済学の研究に力を尽くすことになる。もちろんマルクスは研究活動だけを行っていたわけではない。特に1864年に創立された国際労働者協会(第一インタナショナル)では、中心的メンバーとなり、創立宣言などの起草も行っている。しかし、この時期にマルクスが最も力を注いだのは労働者階級の解放のための理論研究であった。そしてその成果は1867年に『資本論』第1巻として発表され、遂に社会主義思想の科学的基礎ができあがったのである。
■ 社会主義の拡大と福祉国家路線の登場
マルクスが『資本論』を執筆した時代から現在まで資本主義社会は大きな変化を遂げている。19世紀末から20世紀にかけては、先進資本主義国で重化学工業の発展と生産の集積・集中が進み、独占的大企業が大きな力を持つようになった。独占資本主義の時代である。この時期には銀行資本もその規模の巨大化によって経済への支配力を強め、金融寡頭制ともいうべき特徴を帯びるようになる。そして20世紀に入る頃からイギリスやフランス、ドイツなど先進資本主義国は、植民地の再分割をめぐって抗争を繰り広げるようになった。帝国主義の時代の始まりである。そして日本も日露戦争以降、領土再分割競争に参入することになるのである。
しかし、最も大きな事件は1917年10月のロシア革命で社会主義政権が成立したことであろう。当初、資本主義諸国の指導者達は、社会主義政権は短期で崩壊するだろうと考えていたが、1930年代以降その期待は大きく裏切られる。というのは、資本主義諸国が世界恐慌に苦しんでいる時に、ソ連邦は第一次五カ年計画(1928年10月〜33年9月)を成功させ、急速な工業発展をとげていったからである。
そして先進資本主義国はこの世界恐慌から脱出するために経済への介入を強め、国家独占資本主義と言われる時代に入ることになる。1933年からアメリカで実施されたニューディール政策では、不況対策=失業者救済のため公共事業の拡大が実施された。そしてこのような人為的な雇用創出策(スペンディングポリシー)は戦後「完全雇用政策」として先進各国に広がることになる。また、イギリスでナチスドイツとの戦争に国民を結集するために打ち出されたベヴァリッジプラン(社会保険及び関連サービス、1942年12月)に見られる社会保障の充実策も、第二次大戦後に実現される。こうして福祉国家は先進資本主義諸国の多くで共通の目標とされたのである。
福祉国家の実現という目標が資本主義国において一般化した背景は、社会主義の拡大である。東欧や中国も含め、社会主義国が増大するとともに、先進国の労働運動にもその影響が広がり、共産主義や社会主義を掲げる政党が勢力を拡大することになった。そして、そのような社会主義化の脅威に対し、先進資本主義国は国民を資本主義につなぎ止めるため、失業問題や貧困問題への対応を迫られたのである。
■ 新自由主義の拡大
しかし1980年代以降、先進資本主義国における福祉国家を目指す動きに代わり、新自由主義的な潮流が勢いを増すようになる。イギリスのサッチャー政権(1979〜90年)、アメリカのレーガン政権(1981〜88年)の登場が大きな転換点であった。そしてソ連・東欧諸国の経済の行き詰まりが明らかになり、1991年にソ連邦が崩壊するとともに、先進資本主義国の社会主義政党や労働運動の力も大きく低下することになった。
その結果、市場万能論や安上がりの政府論がもてはやされ、社会保障の削減や規制緩和が進められる。グローバルな規模での企業間競争が激化し、労働条件の悪化や貧富の格差拡大が進むことになったのである。まるでマルクスが直面した19世紀的な資本主義への先祖返りとも言えるような状況の出現である。
ソ連邦が崩壊した1991年は、日本で地価のバブルがはじけた年でもある。この時期以降不良債権問題が深刻化し、またデフレ不況のせいで大企業も含め日本経済は長期にわたって停滞を余儀なくされる。しかもグローバルな競争も激化しており、経営難に陥った企業は人員削減と賃金引き下げを推し進め、労働者を犠牲に生き残りを図ることになった。マルクスが「資本論」で明らかにした相対的過剰人口の創出である。失業者は1991年の136万人から2002年には359万人へと急増した(総務省統計局『労働力調査』)。
正社員の削減や賃金引き下げに加え、低賃金で解雇も容易な非正規労働者を増やすことによって賃金コストは大きく削減された。非正規雇用労働者は1984年(2月)には604万人で全体の15.3%を占めるだけであったのが、2018年(1〜3月平均)には2117万人にまでふくれあがり、雇用者全体の37.3%を占めるに至ったのである(同上)。
バブル崩壊で打撃を受けた日本企業は、以上のような賃金コストの引き下げや人員削減、労働強化など、労働者を犠牲にして体制を建て直し、2002年2月から08年2月までは戦後最長の景気拡大と史上最高益を達成する。このような高収益の大きな源泉はマルクスが指摘する労働者からの搾取であり、また競争相手を破綻させることによる集中の促進だったのである。
しかも以上のような貧富の格差の拡大と貧困層の増大(中間層の没落)は、日本だけの現象ではなく、ヨーロッパや米国など他の先進国でも同様に進展した。それらの国では低賃金の移民労働者を増やすことによって、賃金コストの削減が行われた。最近の欧米諸国に見られる移民排斥を主張する民族主義的ポピュリズムの台頭は、その結果にほかならない。社会主義体制の崩壊により、体制転覆の恐れを感じなくなった先進資本主義国の支配層は、労働者への懐柔策を放棄し、露骨に労働者に犠牲を押しつけるようになったのである。資本主義はまさにマルクスの時代に先祖返りしたかのようである。
資本主義的蓄積法則は現代経済がマルクスの時代より巨大化=グローバル化していることにより、一層厳しく貫徹される。国内の企業間競争であれば、生き残った企業への資本の集中が進むとともに、競争に勝利した企業の下で雇用の場が(その規模は縮小されるとしても)一定程度は確保される。しかしグローバル競争では、国境を越えた競争が産業ごとにその都度明暗を分ける形で推進され、競争に敗れた国の雇用はさらに大きな打撃を受けることになる。
1980年代には乗用車、工作機械、半導体など日本の工業製品の輸出拡大がアメリカの雇用を悪化させたとして日米間の経済摩擦が激化した。しかし、デフレ不況期にはシャープ、パナソニック、ソニーなど日本の電機関連の大企業が得意とした半導体や薄型テレビが韓国など外国企業との競争に敗れ、経営悪化が相次ぐことになる。そしていずれも大幅な人員削減や子会社の売却などのリストラ策を余儀なくされたのである。さらに最近では、アメリカの雇用を外国から守ろうとするトランプ大統領の保護政策によって、新たな経済摩擦が燃え上がろうとしている。
以上のようなグローバル化による競争の激化のもとでも、多くの大企業は労働者や下請け企業に犠牲を押しつけることで生き残りをはかってきた。そして日本の大企業も最近では株高・円安の恩恵を受け、高収益を確保している。しかもその多くは無借金経営となり、莫大な内部留保を蓄積しているのである。
■ マルクスによる長時間労働批判と働き方改革
6月29日の参議院本会議で働き方改革関連法が成立したが、その柱の1つが長時間労働の是正である。たしかに日本の労働者の長時間労働の実態はひどいものであり、マルクスが分析の対象とした19世紀のイギリス資本主義を彷彿とさせられる。
19世紀のイギリスでも労働者の劣悪な労働条件を改善するために工場法が制定されている。最初の工場法は1802年に成立しており、その後1831年までに3回も立法措置が繰り返されている。しかし、いずれも違反を取り締まるための制度が未整備であるため、資本家の抵抗によって死文にとどまり、実際に効力ある工場法が成立したのはようやく1833年になってのことであった。
1833年工場法は9歳未満の児童の使用を禁止し、18歳未満の男女についてはその夜間労働を禁止するとともに労働時間を1日12時間以下、週69時間以下に制限するものである。対象が18歳未満の年少者に限定されてはいるものの、その実施を監督する工場監督官制度を定めることによって実効性を持たせたことが画期的であった。そして1844年の追加工場法で、女性労働者も年少者と同様の規制が行われるようになった。
日本においては労働基準法第三二条によって労働時間については原則「1日8時間、1週40時間」と定められ、残業は禁止されている。しかも第一一九条でこの第三二条に違反して残業をさせた場合は「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めているのである。しかし、この労基法の規定はイギリスの初期の工場法のように、ほとんど空文にとどまっていた。というのは、労基法三六条において、労使協定を結び手続きさえ行えば、なんと青天井で残業させても違法にならないからである。
しかし、長期のデフレ不況のもとで人員削減が進むとともに、残された現役労働者の労働強化と長時間労働が恒常化し、労働災害として認定されるような深刻な健康被害が相次ぐようになった。そして、このような長時間労働に対する国民の批判の高まりを背景に、政府も働き方改革に乗りだし、今回ようやく残業時間の上限と上限超過についての罰則も定められることになったのである。
具体的な規制内容を見ると、残業時間については
- 年間720時間、
- 2〜6カ月平均で80時間以内、
- 単月では100時間未満、
- 月45時間を超える残業ができるのは年6回(6カ月)まで
となっている。以上の内容をみると、企業側に配慮し、単月では100時間未満まで可能というような、かなり緩い規制になっていることは否定できない。しかし、これですら従来の規制ゼロの状態からは一定の前進と言わざるを得ないのが日本の現状である。
マルクスはインタナショナルの総務委員会で、1865年の6月に経済学に関する講演を行っている。これが後に出版されマルクス経済学の優れた入門書として知られる「賃銀・価格・利潤」である。そしてそこでマルクスは、長時間労働を次のように鋭く批判している。
「時間は人間の発展の場である。思うままに使える自由な時間を持たない人間、睡眠や食事などをとる純然たる生理的な中断時間はべつとして、その全生涯が資本家のための労働にすいとられている人間は、駄獣にもおとるものである。彼は、他人の富を生産するたんなる機械であり、からだはこわされ、心はけだもののようになる。しかも近代産業の全歴史が示しているとおり、資本は、もしそれをおさえるものがないなら、たえずしゃにむに全労働者階級をこの極度の退廃状態におとしいれることをやってのけるであろう。」
(横山正彦訳『新訳 賃金、価格、利潤』国民文庫、1965年、76頁。『マルクス・エンゲルス全集 第16巻』1966年、大月書店、145頁)。
資本による過重労働の押しつけを阻止するには。単に法律ができただけでは不十分である。職場での労働組合や個々の労働者が声を上げていかなければ、今回の改正法も空文に終わってしまうであろう。長時間労働が深刻な問題になっている現在、マルクスの以上の言葉は心に留めるべき警告である。
■ 階級関係・階級意識の現状
マルクスは『資本論』において、資本主義の発展とともに
「たえず膨張しつつ資本主義的生産過程そのものの機構によって訓練され結集され組織される労働者階級の反抗も、増大する」
(向坂逸郎訳『資本論(3)』岩波文庫、1969年、415頁)
と指摘している。しかし、残念ながら日本においては、必ずしも「労働者階級の反抗」が増大しているとは言えないのが現状である。その要因を明らかにするには、日本における階級関係と階級意識の現状について明らかにすることが必要である。
橋本健二『新・日本の階級社会』(講談社現代新書、2018年)では、賃金労働者を「新中間階級」と「正規労働者」、「アンダークラス」、「パート主婦」に分類し、その階級意識を分析している。このうちアンダークラスとは、パート主婦以外の非正規労働者であり、「所得水準、生活水準が極端に低く、一般的な意味での家族を形成・維持することからも排除され、多くの不満を持つ、現代社会の最下層階級である」(同上書93頁、以下同じ)。
新中間階級は、被雇用者のうちの専門職と管理職と上級事務職である。彼らは自らの労働力を販売し賃金を得ているという点では労働者階級であると言えるが、もともと資本家階級が行っていた労働者の管理・監督や生産設備の管理というような業務を行っているという点で、一般の労働者と区別し、新中間階級に分類されている(61頁)。
現在の日本で深刻化している格差の拡大や貧困の問題を解決するには、所得再分配政策が不可欠である。しかし、著者の橋本氏によれば、この問題について以上の4つの労働者階級の意識はかなり食い違っている。所得再分配政策に対して、アンダークラスの支持は最も強く、パート主婦の支持も比較的高くなっているものの、新中間階級と正規労働者はあまり支持していないというのである(233頁)。これでは労働者階級が一致して格差是正の問題に取り組むことは困難である。
アンダークラスが現状を変革する主体になり得るかというと、同書は否定的である。彼らは相互に連帯する機会をもたずバラバラであること、さらに格差是正の要求が排外主義と結びつく傾向が強いという問題を抱えているからである(246頁)。
全就業者に占める割合は新中間階級が20.6%、正規労働者が35.1%、アンダークラスが14.5%、パート主婦が12.6%である。量的な規模では全就業者の過半を占める新中間階級と正規労働者が重要なことが明らかである。
著者の橋本氏は、これまでは新中間階級に格差縮小に向けた社会変革の主体としての期待を寄せていたという。2005年までの意識調査(SSM調査)では、この層が政治意識が高く、格差の現状に批判的であり、また、戦後の民主化運動や平和運動、反公害運動、最近の反原発運動や安保法制反対運動でも中心的役割を果たし、さらに2009年の総選挙直後の調査では民主党支持率が高く、政権交代の実現にも大きな役割を果たしていたからである(296〜297頁)。
しかし、2015年(SSM調査)と16年(首都圏調査)のデータを分析すると、その新中間階級でも格差拡大への容認傾向が強まっているという。その要因は明らかでないが、民主党政権の挫折が何らかの影響を及ぼしているのかも知れない。また、新中間階級や正規労働者は、貧富の格差が拡大する中でも比較的恵まれた状態にあることから、その現状に安住しがちになっていることも考えられる。
安倍政権が所得再分配政策に否定的な態度を示し、法人税減税や株価引き上げ・円安誘導など大企業優先の政策を推し進めているのも、このような労働者階級内の分裂を踏まえた対応とも考えられる。安倍政権が立脚するのは、企業が成長して高収益をあげれば、労働者や下請け企業にもその恩恵が及ぶはず、というトリクルダウン理論である。
マルクスも「資本論」では資本蓄積の一定局面で労働者の賃金が上昇する場合があることを否定してはいない。しかしそれは永続せず、相対的過剰人口の創出により、(労働者が闘わない限り)賃金水準の低下が引き起こされるというのが資本主義の法則である。しかも日本企業は2002年に好業績のトヨタがベアゼロ回答をして以来、企業収益が改善しても賃金を引き上げることはせず、内部留保をため込む路線を続けてきた。安倍首相が企業に賃上げを要請する「官製春闘」を演じているのも、(最大の理由は労働者階級の自民党支持者を増やそうということであろうが、もう1つの理由は)そうでもしないと日本企業は賃上げを実施せず、トリクルダウンが実現しないとわかっているからであろう。
しかし大企業は、多少のベースアップに応じても、非正規雇用への依存を高めるなどの方法で賃金コストの抑制を着々と進めており、安倍政権の下でも実質賃金は低迷を続けている。しかも安倍政権は社会保障費の切り下げを進めており、将来に対する国民の不安は一向に解消されていない。個人消費が低迷を続けているのもそのためである。
問題は新中間階級や正規雇用労働者が、安倍政権のトリクルダウン政策の欺瞞に気付き、所得再分配政策(格差是正)の必要性を認識できるかどうかである。そしてこの問題を明らかにするためには、この2つの階級の内部構成を分析してみることが必要である。
この問題について橋本氏は、新中間階級はかなり隔たりのある3つのグループに分かれているという興味深い分析結果を示している。それによれば、新中間階級の中の自民党支持の右翼的なグループは14.4%を占め、所得再分配には否定的で自己責任論が強く、政治的には軍備増強・排外主義の傾向が強いという。しかし、38.8%を占める穏健保守のグループは所得再分配には消極的であるものの、軍備重視や排外主義的傾向はさほど強くない。そして残りの46.8%がリベラル派であり、所得再分配を支持する傾向が強く、軍備増強や排外主義への支持も低いのである。しかも橋本氏によれば、正規労働者にも同じようなリベラル層を見出すことができるというのである(299〜301頁)。このように、新中間階級や正規労働者の中で多数を占めるリベラル層こそが民主主義的変革の主体として重要であり、その結集と拡大ができれば、格差是正や貧困問題の解決も大きく前進するに違いない。
■ おわりに
マルクス生誕から今日までの200年間には様々な政治的・経済的事件が勃発し、資本主義も大きな変容を経験した。しかし現在の先祖返りした資本主義の状況を見ると、マルクスが明らかにした法則がそのまま当てはまると言っても過言ではない。マルクスから資本主義の本質を学び、労働条件の改善や格差・貧困問題の解決に向けた取組みを拡大強化することが、当面の最重要課題であることが明らかである。
格差の拡大や貧困問題の深刻化を背景に、最近では「資本論」など、マルクスの古典への人びとの関心が再び高まっている。マルクスの著作は読むたびに新しい発見をもたらしてくれる。現在の資本主義に対する科学的な見方を養うためにも、職場や地域でマルクスの学習が広がることを期待したい。
|