|
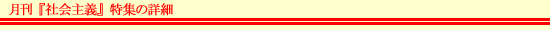
●2017年1月号
■ 150年と100年の歴史との対話を深めよう
熊本学園大学教員 杉田憲道
■ 50年前のこと
今年(2017年)は、カール・マルクス『資本論』第1巻刊行150周年およびロシア革命100周年にあたる。おそらく今年の秋にかけて、いろいろな組織がこれを記念して様々な催し物をおこなうであろうが、社会主義協会も全国各地での集会と記念出版を予定している。
今から半世紀も前のことであるが、向坂逸郎は、『資本論』100年を迎えるにあたって、岩波文庫版に改訂を加えた記念版『資本論』(全4冊)と『資本論入門』を出版した。さらに大内兵衛/向坂逸郎編集の『唯物史観』4号で「『資本論』刊行100年特集」、5号で「ロシア革命50年記念特集」を組んだ。
この記念版『資本論』の「訳者まえがき」で、向坂は、以下のように書いている。
“『資本論』は、百年を生き続けた。そして人類の歴史の存するかぎり生きつづけるであろう。それは、資本主義社会における矛盾の冷徹な余すところなき分析によって、人類の新しい歴史の開始を告知したからである。社会主義を科学にしたからである。さらに、このことによって、歴史の進展を現実にする人間の糧となったからである。つまり、『資本論』は、マルクスという天才の手になった労働者階級の歴史的自覚であったからである。…
マルクスは、この書で資本主義の社会主義への必然性を立証した。それは、われわれにとって、歴史の方向を示すことである。日本の歴史をつくる者は、われわれ自身である。だから『資本論』は、人生の書である (注1)”
この「人生の書」を、労働者にわかりやすく解説するために、向坂自身が「ささやかな『資本論』百年の記念のつもり」と表現して出した文庫本が『資本論入門』(岩波新書)であるが、この本のいたるところで、社会主義社会のことが原則的にふれられている。
“社会主義社会は、むろん計画社会である。しかし、封建社会とちがっているのは、国民が生産手段を社会の所有にして、意識して計画的に運営するという点である。国民によって選ばれた中央機関によって計画される、組織された社会である。…
社会主義的な計画経済であるならば、社会の総労働は、人民の選挙によってなる中央計画機関がこれを掌握している。…
計画社会では、このような中央計画機関が、適当に社会の総労働を全社会に配分することができる (注2)”
このような原則的な立場から、向坂は、現実の社会主義社会にも目を向けた。向坂は、雑誌『唯物史観』のなかで、「生まれて百年、『資本論』は、あらゆる苦難をこえて生きつづけた。『資本論』が予言したとおり、『資本論』の論理にしたがって、いまから50年前に、ロシア社会主義社会が生れた。いまマルクスの祖国ドイツにも社会主義が成立し、発展している (注3)」と述べた。
ドイツの社会主義については、後で関説するが、ロシア革命について、向坂は、その世界史的意義(とくに、十月革命における一般性)をつぎのように強調した。
“現代における階級および階級闘争は、資本主義の発展と結ばれて発展し、この階級闘争は、プロレタリア階級の独裁に必然的に発展する。社会主義革命は、プロレタリア階級の独裁の実現である。そして、この階級独裁は、階級対立の存在しない社会に発展する。この社会主義革命の一般性は、そのままロシアにおける社会主義社会の実現と発展に、貫徹されている。…
レーニンは、社会主義革命が、具体的に現実の問題となった時代において、マルクシズムの基本的理論を明らかにした。それは、帝国主義の時代に適用されたマルクシズムである。レーニニズムは、マルクス・エンゲルスの正系の嫡子である。…
今後おこる何れの国の社会主義革命といえども、ロシア大革命の特殊な在り方の下に、その土台をなしているマルクス・レーニン主義の一般性の特殊な適用形態である。十月革命は、世界における社会主義革命の突破口であった、という意味は、理論的にはここにあると考えなければならない (注4)”
確かに、第二次世界大戦後、ソ連邦を中心として社会主義諸国は著しい発展を遂げたし、さらに飛躍するかのように見えたが、しかし、その社会体制内部ではしだいに様々な問題が露呈しはじめ、自己解決能力を失っていった。こうして世紀末に、20世紀最大の事件と言っても過言ではない「社会主義世界体制の崩壊」がおこったのである。
■ 崩壊原因の徹底的な究明に向けて
社会主義世界体制が崩壊したにもかかわらず、依然として社会主義をめざそうとしている人々(組織)は、緊要な課題に直面した。それは、「この体制が何故に崩壊したのか」、その原因を徹底的に究明することであり、さらに、「あらためて魅力ある社会主義」を提起することであった。社会主義協会も、この使命を担わなければならなかったことは言うまでもないことで、それゆえに、2002年3月、第35回全国総会で『社会主義協会提言の補強』が採択され、以下のような歴史的総括がおこなわれた。
“第二次大戦後、復興と社会主義建設を進めたソ連は、1950年代後半から60年代初頭にかけて経済成長率の鈍化と売れ残り商品の滞貨などの問題に直面した。東欧諸国も同様で、65年のコスイギン改革をはじめとして、各国で相次いで経済改革が試みられた。この60年代改革は、生産力の高まりに応じて経済を外延的・量的成長から内包的・質的成長に転化することによって、生産と消費の調和、国民生活の向上とより成熟した社会主義経済体制の確立をめざしたものであった。…
60年代改革は経済指標の改善などの短期的成果はあげた。しかし、… 60年代改革は一方では社会主義における商品・貨幣・利潤などの利用に関する理論的未成熟によって、他方では国家経済管理機関の官僚主義や企業の不適切な利潤極大化行動などにより歪められ、中途半端のまま短命に終わった。…
ソ連・東欧社会主義体制崩壊の主要因は、…60年代改革で追求された課題が未達成で温存され、70年代後半以降に経済的、政治的、社会的矛盾が蓄積したことにあった。生産力の高まりに応じた社会主義的経済計画・管理制度はついに構築されず、経済の内包的・質的成長への転換は実現されなかった (注5)”
このような分析視角は、昨年9月に北京で開催された中国社会科学院マルクス主義研究院とのシンポジウム(テーマ:『資本論』、ロシア革命と現代社会主義)での意見交換を通して、さらに深まっていったように思う。それは、主催者の金民卿(マルクス主義研究院マルクス主義中国化研究部主任)が行なった以下の集約に表れている。
小笠原福司(社会主義協会事務局長)は、十月革命の意義についてマルクス主義の立場から報告をし、さらにソ連・東欧諸国の崩壊、挫折についても報告したが、とくに、崩壊の原因について60年代経済改革の失敗にかんする分析から、ソ連崩壊の原因を探るというたいへん興味深い報告を受けた。それに対して、中国側は、政党による政治指導の不十分さに、崩壊の主原因があるという観点からの報告をおこなったが、この2つの視点を合わせると、社会主義体制崩壊の原因の研究が完全なものになるのではないかということが、この集約の内容であった。
中国社会科学院との共同研究の成果は、崩壊原因のみならず、『資本論』の研究領域の拡大・深化にも繋がったことを、筆者は強調しておきたい。とくに社会主義社会において果たす『資本論』の役割についての研究に焦点が当てられたことが、それであった。
『資本論』は、言うまでもなく、資本主義社会の経済的運動法則を分析した書であるが、それとともに本書のいたるところで社会主義社会についても論述している。
フリードリッヒ・エンゲルスは、この点に関して、以下のように書いている。
“とうとう1867年、ハンブルクで『資本論。経済学批判、第1巻』 ──マルクスの経済学的=社会主義的見解の基礎と、現存社会つまり資本主義的生産様式とその諸結果とにたいする彼の批判の大綱とを叙述したその主著 ──が出版された (注6)”
この「経済学的=社会主義的見解の基礎」という立ち位置は、『資本論』の果たす今日的役割にとって様々な観点からきわめて重要であろうと、筆者は考えている。
■ 『資本論』の具体的適用をめぐって
ひとつは、『資本論』のなかで展開されている未来社会論を無媒介的に現代社会に適用することにかんする方法論上の問題である。例えば、『資本論』のなかに表現された「各個人の十分な自由な発展を根本原理とするより高い社会形態 (注7)」をベースにして、旧ソ連邦や中国のような現存した(する)社会主義諸国を「人間の自由を抑圧する専制社会である」と規定して、社会主義や社会主義への過渡期とは無縁の社会であると位置づけることへの疑問である。
“未来社会論とは、科学的社会主義の事業にとって、いわば、本業にかかわる分野です。
スターリン以後のソ連社会は、社会主義とも社会主義への過渡期とも無縁な人民抑圧型の社会であり、こんにちの中国も『社会主義をめざす道』に足を踏み出したところであって、社会主義に到達した国でも、私たちがめざす社会主義を体現した社会でもありません (注8)”
これは、『資本論』のなかで表現された未来社会を、とくに「自由の保障」という観点から無媒介的に現状にあてはめて分析する手法をとっているが、方法論には大きな問題があると、筆者は考える。
『資本論』が「現存した(する)社会主義社会」のなかで具体的にどのように適用されていったのか、そして、そのさいの問題点は何であったのかを検証し、分析するなかから、今日における社会主義社会への実現(社会変革)に向けての新たな課題が提起されるのではないかと考えるからである。例えば、東ドイツにおける社会主義建設に、『資本論』がどのように具体的に適用されたのであろうか。このことを検討することは、今日の社会主義、これからの社会主義を考えるうえできわめて重要な地歩を占めているのではないか。一例を示すと、こうである。
マルクスは『資本論』の第3巻で以下のように書いた。
“商品が資本家に費やさせるものと、商品の生産そのものに費やさせるものとは、もちろん、2つのまったく違った大いさである。…
それゆえ、商品の価値のうちただその商品の生産に支出された資本価値を補填するだけのいろいろな部分を、費用価格という範疇のもとに総括することは、一面では資本主義的生産の独自な性格を表わしているのである。商品の資本家的費用は、資本の支出によって計られ、商品の現実の費用は労働の支出によって計られる。だから、商品の資本家的費用価格は商品の価値または商品の現実の費用価格とは量的に違うのである。
… この価値部分の独立化は、商品の現実の生産で絶えず実際に行なわれている。というのは、この価値部分はその商品形態から流通過程を経て絶えず再び生産資本の形態に再転化しなければならず、したがって商品の費用価格はその商品の生産に消費された生産要素を絶えず買いもどさなければならないからである (注9)”
■ 東ドイツの『資本論』適用の検証とこれからの課題
前記のマルクスからの引用文に関連して、以下の三点が現存した東ドイツ社会主義経済に具体的に適用された。
第一は、「商品の現実の費用は労働の支出によって計られる」という考え方を、社会主義における「社会的生産コスト」として概念化したことである。「社会的生産コスト」とは、ある製品の製造に支出された社会的に必要な生きた労働と対象化された労働の貨幣表現である。「社会的生産コスト」で、ある製品の生産のために費消された価値と新たに付け加えられた価値とが把握される。つまり、「社会的生産コストと製品価値は、同一概念である(注10)」がゆえに、社会主義においては、「社会的生産コスト」は労働の支出全体、したがって剰余労働をも体現することになるのである。
第二は、『資本論』の「価値部分の独立化」である。社会主義においては「製品の生産のための労働の支出は、労働時間で直接的に測定不能であったので、この原価と純所得の独立化は、社会的必要労働支出を貨幣の助けをかりて測定し、価格に反映することによってはじめて可能である」という論理がマルクスの言葉をかりて正当化されたことである。「今日、労働支出全体の直接的な把握のための諸前提は存在しない。社会主義条件の下で労働支出全体の客観的に不可欠な測定は、それゆえに価値の独立的部分にもとづいて、すなわち原価、純所得ないしは利益にもとづいておこなわれねばならない (注11)」
第三は、この「価値部分の独立化」が「商品の現実の生産で絶えず実際に行なわれている」という視点からの指摘である。「社会主義コンビナート・企業は、相対的に独立・自律した経済単位として生産フォンドと流通フォンドを処分する。そのフォンドの循環と回転にたいしてコンビナート・企業は自ら完全に責任をもつ。このプロセスのなかで、生産された製品の価値の一部分が独立し、原価として現象する。… 原価のこの独立化は、貨幣形態においておこなわれている (注12)」
『資本論』を以上のように理解し、適用していった「現存した東ドイツ社会主義」は、一方では「生産手段の共有を土台」にした社会であったが、他方では「生産者が生産物を交換しない」という社会ではなかった。つまり、社会主義のなかに商品・貨幣関係が内在した社会であった(注13)。
こうした計画経済と市場経済がミックスされた社会主義においては、本来の社会主義において労働の支出をベースにした時間計算と数量計算というシステムに価値計算が付け加えられて、いわばその調和と対立という緊張関係のなかに社会主義が現存していた(いる)ことになる。
こうした歴史的事実を出発点にして、これからの課題について考えてみよう。例えば、中国の社会主義初級段階における『資本論』の占める地歩、つまり、中国が現在、『資本論』をいかに有効に適用しているのか、あるいは、今後どのように適用していこうとしているのか、大いに関心のあるところである。とくに、中国社会主義における株式会社の地歩に関して、これを『資本論』に関連づけて、中国は、どのように理論化するのであろうか。
特殊性のなかに、必ず一般性が潜んでいるがゆえに、社会主義のこれまでの歴史との対話をさらに一層深めてゆかなければならない。この対話は、これからの社会主義の在り様だけではなく、社会主義社会をめざすさいの社会変革の道筋とも切り離しがたく結びついているからである。
(注)
(注1) マルクス『資本論』第1巻、向坂逸郎訳、岩波書店、1967年、訳者まえがき──『資本論』百年を迎えるに当って──p.iii〜vii
(注2) 向坂逸郎『資本論入門』、1967年、p.136〜p.150
(注3) 向坂逸郎「『資本論』の意味するもの」(大内兵衛/向坂逸郎=編集『唯物史観』4号、1967年、p.14)
(注4) 向坂逸郎「十月革命の世界史的意義」(大内兵衛/向坂逸郎=編集『唯物史観』5号、1967年、p.19〜20)
(注5) 『社会主義協会提言の補強』、2002年、p.124〜129
(注6) エンゲルス『カール・マルクス』、1877年、p.108(マルクス・エンゲルス全集、第19巻、大月書店)
(注7) 『資本論』第1巻、p.771(マルクス・エンゲルス全集、第23巻、大月書店)
(注8) 山口富男『科学的社会主義のすすめ』、雑誌『経済』、2016年8月号、p.111
(注9) マルクス『資本論』第3巻、p.34〜35(マルクス・エンゲルス全集、第25巻、大月書店)
(注10) Woerterbuch der Oekonomie Sozialismus, Dietz Verlag, 1983, S.332
(注11) H.Marx / F.Matho / U.Moeller / G.Schilling ; Die wirtschaftliche Rechnungsfuehrung, Dietz Verlag, 1989, S.113f.
(注12) Ebenda, S.113
(注13) 「東ドイツの検証」(注の10、11、12)の箇所は、中国社会科学院で開かれたシンポジウムで筆者が報告した内容の一部である。
|