|
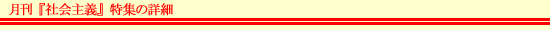
●2006年6月号
■ 生産性三原則への信頼回復
―「労使関係白書」再刊のねらい―
(松永裕方)
■「労使関係白書」再刊の理由
社会経済生産性本部は、その前身である日本生産性本部が1955年に設立されて50年目にあたる今年、「新版・労使関係白書」を発表した。だが「労使関係白書」(以下「白書」)といっても、ほとんどの読者にとってはなじみが薄く、日本経団連の「経営労働政策委員会報告」ほどには知られていないのが実情だろう。しかも、最近の10年間は発行されていないのだから当然のことではある。
ではなぜ、生産性本部は「新版」と銘うって再刊することにしたのだろうか。
生産性運動は、その創成期は「力と力のぶつかり合いであった対立的労使関係から、協議と協力を基調とする近代的労使関係へと転換するための歴史的な取り組みであった」が、「その取り組みの支柱として、毎年初春に、産業界労使に対して時代認識と労使の課題を提示し、信頼に基づく健全な労使関係を構築するための指針を提供してきたのが『労使関係白書』であった」。その「白書」は、日本生産性本部に設置された「労使協議制常任委員会」によって、1966年以来30年間に亘り発行されてきた。
しかし、96年以降の10年間にそれが途絶えた。その時期は、バブル崩壊後の蕫失われた10年﨟といわれた不況期とほぼ重なる。休刊の理由については、直接には何も述べられていないが、この間に、「生産性三原則の『揺らぎ』という現実」が生じたことは認めている。
しかしその後の情勢の変化、特に雇用形態や価値観の多様化、個別的労働関係の進展、グローバル化、少子高齢化などの進展は、もはやこの「揺らぎ」を放置するわけには行かなくなった。この運動への労働組合の「信頼」が失われれば、「社会不安や社会の混乱を招く」事態にもなりかねない。だから、「生産性三原則の意義と重要性を再確認しつつ、新たな時代の中での方向性を整理」する必要が生じた。10年ぶりに再版する理由が、ほぼ以上のように述べられている。
■ 生産性三原則
生産性向上運動といっても、合理化運動と何ら異なるものではない。しかし、戦後この運動をすすめるには、なによりもまず、戦前の産業合理化運動が恐慌と戦争に結果した記憶を払拭する必要があった。そのために採用された新しい名称が生産性向上運動にほかならない。そしてこの運動は、単なる生産技術や経営技術の改善等の技術的側面にとどまるものではなく、また、「経営者など特定階層の利益を代表する」ものでもなく、労働者はもとより、全国民の利益を増進させる運動――「国民運動として推進」するものであるとされたのである。
この運動の中心を担う組織が日本生産性本部であるが、アメリカの援助の下、政府の強力な指導により設立された。その設立総会では、運動の趣旨が次のように述べられている。
「生産性の向上は、資源、人力、設備を有効かつ科学的に活用して生産コストを引き下げ、市場の拡大、雇用の増大、実質賃金ならびに生活水準の向上を図り、労使および一般消費者の共同の利益を増進することを目的にするものである」。
「生産性の向上は生産を担当する経営者、労働者はもとより、広く全国民が深い理解をもって、これに協力することなくしては、到底十分な効果を期待することはできない」。
このように、生産性向上運動は全国民の共同の利益を増進させるためのものであるとされた。「白書」の冒頭にあるように、この運動は当時アメリカで唱えられていた、「ピープルズ・キャピタリズム思想」の影響を受けてすすめられた。それは、政府の適切な対応によって、労働者の窮乏、恐慌などの資本主義の内在的矛盾を回避することが可能であり、その上で行なわれる企業の生産力の向上は、労働者の賃金引上げとともに、社会保障の整備に貢献する。生産性向上運動は、「資本主義改革の思想」にもとづく運動だとされているのである。
だから生産性向上運動の中心組織は、当時の日経連や経団連のような、誰が見ても資本家側の組織であってはならなかった。政府、経営者、労働者が加わった組織にして、中立的な装いを持たせる必要があったのである。
このような思想にもとづいて、運動の基本と掲げられたのが次の「生産性運動の三原則」である。
1、生産性の向上は、究極において雇用を増大するものであるが、過渡的な過剰人員に対しては、国民経済的観点に立って、能う限り配置転換その他により、失業を防止するよう官民協力して適切な措置を講ずるものとする。
2、生産性向上のための具体的な方式については、各企業の実情に即し、労使が協力してこれを研究し、協議するものとする。
3、生産性向上の諸成果は、経営者、労働者および消費者に、国民経済の実情に応じて公正に分配されるものとする。
「雇用増大」「労使協議」「成果の公正配分」といわれるものである。
■ 生産性運動と労働運動の二つの潮流
生産性運動で最も力が入れられたのは労働組合の取り込みであるが、これへの態度をめぐって、日本労働運動は大きく2つの潮流に分かれた。当時の全国組織の生産性向上運動への基本的態度を、以下に簡単に見ておこう。
総評は1956年3月に、要旨次のような「生産性向上運動に関する態度」を決めている。
「生産性向上運動は第一に、搾取強化のありとあらゆる方法を全面的に動員して、資本の利潤を極限まで拡大しようとする。…第二の特徴は、それが『国民運動』として思想攻撃を展開し労働者の階級意識をマヒさせ、労働組合を御用化して事実上これを解体しようとする階級協調のカンパニアだという点にある。…
したがってわれわれの闘いも、階級協調運動としての本質を徹底的に暴露し、生産性向上運動は資本主義のもとでは搾取強化しかもたらさないし、労働者の生活を改善しうるのは労働組合に団結した労働者自身の闘争以外にないという階級的な思想をほんとうに大衆のものとし、生産性向上運動に対して全面的な反撃を加えることに、第一の重点をおかなければならない。この闘いを土台にしてはじめて、搾取強化の一つ一つの現われとの闘いが本格的な筋金のはいったものになる。…
この闘いの土台は、搾取強化のあらゆる攻撃と闘う職場闘争にある」。
もう一方は、当時の総同盟と全労(両者は後に同盟に)であるが、両組織は早くも1955年7月に基本的態度を決め、この運動に参加した。総同盟の「八原則」の要旨は次のようなものである(全労は「五条件」で主旨はほとんど変わらない)。
生産性向上運動は、個々の合理化運動、能率運動とは異なり、日本経済の自立と、国民生活の向上を目指す総合的施策に貫かれた運動であること。労働強化による企業収益の増大を目指すものではなく、労働条件の向上、実質賃金の向上をもたらすものであること。経済の拡大、発展を通じ雇用量の増大をもたらすべきものであり、使用者及び政府は失業の危険を除き雇用の安定を図るための措置を講じなければならないこと。資本の集中をもたらすものでなく、中小企業の安定とその労働者の生活の向上をもたらすものであること。得られた諸成果は、物価の引き下げ、労働条件の向上及び設備の更新のため適正に充当されるべきこと。産業民主主義の徹底と合理的な労使関係の確立が不可欠の要件であること。などである。
総評は労資関係を階級関係ととらえ、自らの団結だけが労働者の生活を改善する力であると呼びかけた。これに対して総同盟と全労は、企業や国民経済の発展という点では労使の利害は共通しているとし、生産性運動への参加を呼びかけた。労使協調路線といわれる所以であるが、経営側への全面的な「信頼」がその特徴だといえる。生産性向上は労働強化や搾取強化をもたらすものではなく、必ず労働条件の向上、実質賃金の向上につながると言うには、経営者への全面的な信頼が欠かせないからである。
■ 生産性運動の「成果」
「白書」は、生産性三原則は「わが国の経済成長を支える重要な基盤」となり、それが良好な労使関係の確立によって可能になったと言っている。労働組合の「自主的な運動への参加」が促されただけでなく、それまでの日経連の「賃上げ抑制」、労働組合への「否定的な姿勢」にも明らかな変化が生じ、「階級対立至上論を克服した新しい労使関係論を形成する」ことができたというのである。そして、生産性三原則が着実に浸透してきた結果、次のような大きな成果が得られたと言っている。
「労使協議を通じて広く共通の理解を築くとともに、現場でも小集団活動に代表されるような労働者の主体的な業務改善の取り組みを進展させた」。
「低水準の失業率を長期間維持してきた。そうした中で安定的な雇用関係の下において、長期にわたる能力の開発・向上と労働者の高いモチベーションの維持が可能になった」。
「春闘方式による賃金決定機能は、年々拡大する経済規模にあわせて、経済合理性に基づいた成果の公正配分という面で大きな役割を果たしてきた。実際、この間の賃金水準は飛躍的に上昇し、国民生活も着実に向上してきた。労使協議制についても、上場企業では導入比率が九割を超えるに至り、雇用・労働条件に関わる諸課題はもとより経営課題についても協議されるようになった」。
「労使協議制を通じて産業民主主義の考え方を普及させ、企業における従業員重視の経営姿勢の確立と従業員集団の結束力の向上に大きく貢献した。…日本型経営の特徴とされる年功主義や長期雇用慣行も形成され、…企業は中長期的な視点から人材育成の機会を提供していくとともに、労働者も安定した職業生活のもとで仕事に対する長期的なコミットメントを高めることができるようになってきた」、等々。
しかし「白書」は、「わが国経済の拡大への好循環構造」がなければ、こうした成果も得られなかったと言っている。次のような叙述がある。すなわち、技術革新が「雇用機会の減少や労働密度の強化をもたらすものだけであれば、生産性向上は労働者にマイナスの影響を与えるもの」となるが、それは「企業の競争力を高め、経済発展や国民生活の向上を実現させるための最大の手段であり、当時においても、こうした点を共通認識として持つことが課題であった」、と。分かりにくい文章だが、要するに、経済が成長していれば、技術革新が失業問題に結びつくことにはならず、矛盾は隠せると言いたいのであろう。
「生産性三原則」の第一は「雇用増大」の原則といわれるものだが、生産性向上が「過渡的」に「過剰人員」が出ることを否定してはいない。資本主義の下では、機械化・近代化は本来、労働の節約を主目的に行なわれるものであるから、生産性本部といえども、失業に至る現実を否定することはできないのである。だが機械化がすすむことは、機械製造の業種を拡大し、それが関連産業に波及するといったように、生産性向上は一般に経済を発展させるから、いったん失業しても、そのうちに新たな働き口が見つかるだろう、というのである。生身の労働者にとっては、「過渡的」な期間がどのくらいかは死活問題であるが、経済が「拡大への好循環構造」にあればよいという主張である。第三原則にしても、生産性向上の成果が必ず「公正に分配」される保障があるわけではない。経営者の善意を信ずるほかはない。だから、「労使協議」の第二原則が重要になるのであり、労使の信頼関係を確立し、生産性精神をもたせるための中心的方策として、「労使協議制」の普及・拡大が図られたのである。
「生産性三原則」の破産
経済拡大の「好循環構造」がある間は、生産性向上運動はすべてうまく行くように見えた。しかし、バブル崩壊後の不況期に、生産性三原則を取り巻く環境は大きく変化した。「白書」も「生産性運動三原則」に「揺らぎ」が生じたことを認めている。だが現実は、「揺らぎ」などという生易しいものではなく、生産性運動の論理の破産ともいえる深刻な事態であった。
「白書」自身も、バブル崩壊後「生産性三原則」が持っていた「生産増強あるいは経済成長政策のイデオロギーとしての機能」が失われたと指摘し、次のように述べている。
経済力や生産力のさらなる向上を目指して働こうという労働者のインセンティブの喪失。ライフスタイルや価値観の多様化。グローバル化に伴う国際競争の激化の中での生産拠点の海外移転・産業空洞化の進展と雇用機会の喪失。少子高齢化。仕事の仕方や賃金などの報酬体系の変化。企業の業績の不安定化。雇用の長期的な安定性の揺らぎと非正規雇用の増大(もっとも「白書」では、非正規雇用の増大は、企業の「労働力のフレキシブル化や総額人件費抑制」より、働き甲斐を求める労働者のニーズの方が大きいかのように描かれている)。成果主義・業績による査定分の高まり。労使協議の「空洞化」(労働組合の力のバロメーターである組織率の低下、労働組合の存在と集団的労使関係の意義の低下という、2つの側面から労使協議の「空洞化」がすすんでいると指摘している)、等。
要するに、生産性向上によって雇用は増大し、賃金も上がり、国民の生活水準も向上するというこの運動の理念が、空文句にも等しくなってしまったのである。社会保障の充実に貢献するという「資本主義改革の思想」も危うくなってしまった。労働者が懸命に働いて招いた結果は、失業率の増大であった。5%台から現在は4%台に低下したとはいえ、70年代の1%台、80年代の2%台に比べれば倍増以上である。失業率が3%を超えた時期から「白書」が休刊になったのは偶然ではなく、「雇用増大」の原則が通用しなくなったからであろう。また、労働者が懸命に働いて企業に貢献しても、その儲けは海外に移されて人員削減の要因になるだけでなく、国際競争を理由にした賃金引下げの圧力にもなる。長期雇用の慣行は崩れ、低賃金の非正規雇用労働者への置き換えがますますすすむ。総務省統計局の04年労働力調査によれば、平均年収は正社員の453万円に対して、パートタイム労働者は110万円でその1/4にも満たず、派遣社員は213万円で47%に過ぎない。
ではこの間、資本家側はどういう主張をしてきたのだろうか。95年には、旧日経連が「新時代の『日本的経営』」を発表し、雇用・就労形態を3つに分ける「雇用ポートフォリオ」の採用、雇用形態毎に成果主義賃金、年俸制、時間給・職務給などに分ける複線的人事制度の導入を提唱した。そしてこれをすすめるために、労働基準法の改正など労働部門の規制緩和を、政府に対して強く求めた。重要なことは、経営側が求めた雇用流動化政策は、ことごとく実現していったことである。生産性を上げても雇用安定の保証はないどころか、ますます不安定化と賃金切り下げがすすむという事態になったのである。
この間の「労働問題研究委員会報告」(日経連と経団連の統合後の03年からは「経営労働政策委員会報告」)を見れば明らかなように、資本家側は規制緩和による自由競争の促進とリストラ合理化の推進、総額人件費の抑制(02年以降はベアゼロ、定昇凍結から賃下げまで主張)、他方で法人税の引下げなどの施策と主張を、不況下にいっそう強めた。
企業は儲け第一主義に走り、競争に勝つためには手段を選ばず、賃下げや人減らし合理化を競い、これをやる企業ほど評価されて株価が上がるという状況が生じた。そしてこの後には企業不祥事が相次いだ。製品の不正表示や隠蔽工作、安全対策の手抜きによる大事故の続発などである。企業倫理は地に落ち、日本経団連が繰り返し「企業倫理の確立」を経営者に呼びかけざるを得ない状況になった。
しかしこの間、労働組合はほとんど抵抗なしにリストラ合理化を受け入れ、賃上げ要求も自粛した。ほとんど抵抗もせず、要求もできない労働組合では、企業の不祥事を糺す力も持ちえなくなる。不払い残業(サービス残業)の蔓延は、企業を規制できない労働組合の現状を象徴している。個別紛争が増えるのも、個々の労働者への攻撃が激化しているのに、労働組合がこれを取り上げて闘うことをしなくなったからでもある。
中立的組織であるはずの生産性本部は、この間、経営側の横暴をなすがままにした。99年には、ワークシェアリングに関して、残業をゼロにすれば全産業で170万人程度の雇用機会に相当すること、サービス残業がなくなるだけでも、全産業で90万人程度の雇用機会が生まれるという、興味ある提言を行なったが、具体的運動を提起することはなかった。
抽象的な新時代の生産性概念
「白書」の再刊は、「生産性三原則の意義と重要性を再確認」し、「新たな時代の中での方向性を整理する」ためだとされている。そこで、「白書」が言う再構築の内容を見てみよう。
「白書」はまず、「生産性三原則」がもつ「普遍的な価値」を確認した上で、これを企業レベルだけでなく、社会システムまで含めたマクロレベルで再評価する必要がある、としている。「三原則」はもともと国民全体の問題とされていたはずだが、あらためて社会的レベルでの考え方の重要性を強調するのである。雇用、所得保障などのセイフティーネットの整備、税、社会保障など負担と給付のバランスなど、社会全体の制度・システムを「より強靭なものにする志向を持つべき」であり、これを「民力」の向上と言っている。生産性向上の効果を、雇用拡大や労働条件の向上など企業内的に考えるのではなく、社会全体の制度・システムを改善するものと考えよ、という主張のように思われる。しかしこれは、現実にすすんでいる社会保障の全般的な制度改悪の中で、説得力ある主張にはなりえていない。「マクロ的な視点」といった、きわめて抽象的な概念に逃げ込んでいるのである。
では、「生産性三原則」の各原則については、どのように再評価するというのであろうか。
まず、「雇用増大・失業防止」に関しては、失業率が高くなったのは事実だが、「国民の豊かさ」は高まったのだから、「雇用の質」を問うべきだと言う。新分野の開拓による雇用創出を言ってはいるが、もはや雇用の量的拡大は望めないのだから、「質」を考えよという主張である。仕事の分かち合い(ワークシェアリング)による雇用機会の確保、また、労働移動が不利にならない施策の整備―失業時の所得保障、再就職の支援、教育機会の付与や援助、雇用のセイフティーネットの整備など、さらに、働くこと自体の価値を考える―労働者のキャリア形成、ワーク・ライフバランス、などを指摘しているが、これらを、「雇用増大」に代わる生産性運動の新たな原則にするという主張のように思われる。
「労使協議」の原則については、労働者の労働組合に対する関心の低下、「労働組合の意義そのものが問われる」状況、また、労使協議の担い手の問題(労働組合役員が会社の「キャリア・ルートとして一時だけ就任」することが多く、「知的財産」がうまく継承できない)、さらに、企業の枠組みの変化(企業再編、持ち株会社によるグループ化、グローバル化、就業形態の多様化など)という状況の中で、労使協議を「どう維持・強化」していくかという課題に直面していると言っている。労使関係が持つ「重要な位置付け」は変えてはならないから、「原点に戻った論議」と「新しい発想に立った推進方策」への切り替えが必要だと言うのだが、具体的に挙げているのは、「多元的な協議システム」の発想と、「現場力」の復活の観点から「現場」と経営方針を「対話」させる場としての労使協議の機能を高める必要、ということだけである。
「成果の公正配分」については、「パイ」が拡大しない時代には、その考え方を変えていく必要がある、としている。総額人件費の抑制、雇用確保のための賃上げ断念、ワークシェアリングによる賃金の変更、株主重視の経営姿勢などの必要から、成果の「配分」については、「その枠組みから問い直す必要」が生じていると言う。賃金については、「十分な賃金」というだけでなく、「公正で納得できる賃金」であることを重視すべきだとしている。要するに、「パイ」の拡大ではなく、小さくなった中での分かち合い、賃金も全体の底上げではなく成果による配分を、「公正配分」と理解せよという主張である。また、一般消費者より、株主への配分を重視せよということである。
こうした「生産性三原則」の解釈の変更を求めつつ、「新時代における生産性の概念」の再構築の視点としてあげているのは、以下の四点である。
①企業を取り巻く環境変化に対する最適な行動選択を行うものであること
生産性を単に量的拡大の手段と捉えるのでなく、「変化への対応」に必要な知恵と行動の表われと理解することが必要に。これを「知力」へ接近と言っている。
②企業という集団的枠組みに加えて「個人」をベースにした取り組みであること
集団的枠組みだけでなく、「個人対企業」という個別的労使関係の視点を持つことが重要。
③資源生産性(生産要素)「効率性」だけでなく「共生」など多様な評価軸を持つものであること
④企業内だけでなく社会システムも含めたトータルな解決を目指すものであること
生産性三原則は、一つの企業のレベルでなく社会的なレベルで考えていかなければ成り立ちにくくなっている。
「生産性三原則」の論理は、バブル崩壊後の不況の中で無残にも崩れてしまった。生産性向上に協力してきた労働組合には、「三原則が確実に守られていることへの『信頼』があった」が、「それが今日的な状況の中でゆらいでいる」のである。しかも、その後の景気回復の中でも、財界とその政府は「成果」の「公正配分」に応じようとはしていない。「信頼の揺らぎ」をこれ以上放置することは、協調的幹部の存在を危うくし、労資協調路線を危機に陥れることになりかねない。「生産性概念の再構築」によって、「信頼」の回復が急務となり、「白書」が再刊されたのである。
しかし「白書」は、「再構築」の方向を明確に示し得たとはいえない。賃上げではなく、成果主義賃金を「公正な成果配分」と考えよといった、経営側の政策の後押しであることは明確だが、肝心な点はすべて抽象論で包みながら「信頼の創造」を説くことだけに終わっている。
だが今必要なのは、「信頼」が裏切られたことを嘆くことではない。いくら経営者の善意を信頼したからといって、資本主義の下では賃下げや人減らし合理化がなくなるわけではない。「労働者の生活を改善しうるのは労働組合に団結した労働者自身の闘争以外にない」と呼びかけた総評の方針、労働運動の原点を、いまこそ思い起こす時ではないだろうか。必要なのは、犠牲の一方的な転嫁を許さない労働者の団結の強化と意識の向上であって、資本家の善意に頼る「信頼」ではない。
|